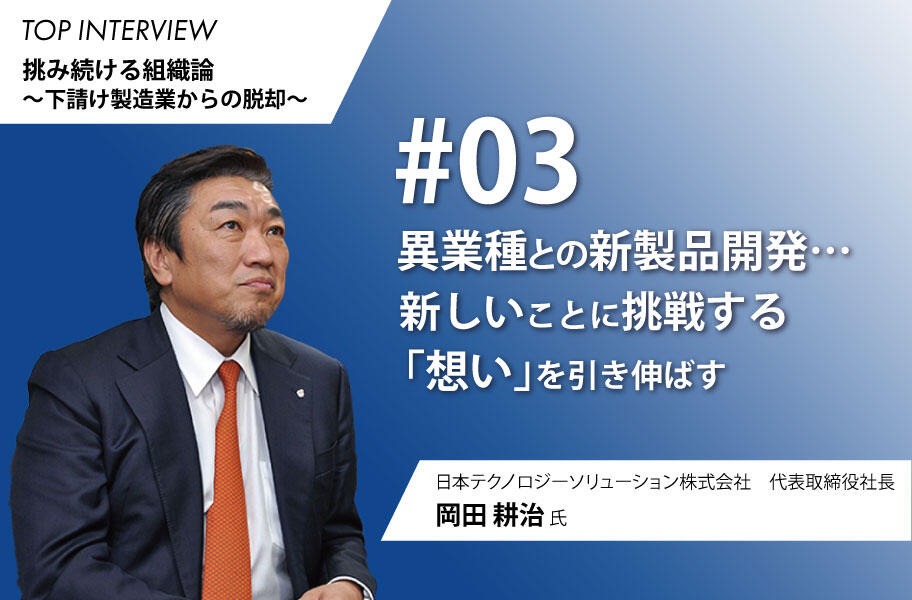
革新的な技術や製品を作り、世に送り出すだけでなく、他の企業と事業を共創し、メディアとして情報発信もする。製造業という枠にとどまらない多様な事業を生み出し新しい時代を創る、それが日本テクノロジーソリューション株式会社である。
今回は、アライアンス事業や社内施策などで仕掛けている、さまざまな「新しいことへの“挑戦”」について、なぜ、そしてどのような想いで進めているのか、代表取締役社長の岡田耕治氏のお話を伺っていく。
1. 1社で何かできる時代ではない
メディア事業を自ら展開する製造業、というだけでも非常にユニークな会社だと思いますが、さらに貴社はアライアンス事業も手掛けていらっしゃいます。どのようなきっかけで始めたのでしょうか。
弊社では経営理念を制定した20年後の2021年に、「地球をワクワクに変える」というパーパスを新たに設定しました。
今、そしてこれからはもう、社会課題に対して1社で何かできるという時代ではないと思っています。
以前は「コラボレーション」「アライアンス」「パートナーシップ」といった言葉が苦手でした。お互いにシナジーを生み出すものがないまま見せかけで手を組んでしまうと、形だけで満足して本物は立ち上げられない……それよりも少数精鋭として1社でやった方がスピードも速いと思っていました。
しかし新たにパーパスを設定する中で、いろいろな会社が一緒になってやっていく方が、より大きなこと、面白いことができそうだと思ったのです。
会議室に飾られているのは絵本の「スイミー」。小さな黒い魚・スイミーは仲間たちに呼びかけて団結し、大きな困難を乗り越える。
そこでいろいろなところと組んでいこうと思い、その領域を事業ドメインの一つとして組み込みました。人間はどうしても慣性の法則が働いてしまい、今までと同じことを同じようにやった方が楽だと思ってしまいます。ですから、「パートナーシップを組む」と明確に掲げた方が、アライアンス事業を進める際の初動がスムーズになると考えました。
同じ事業を続けているとだんだんスループットの効率化に目が行きがちになり、個々の業務の中で閉じている方が楽になってしまうかと思います。特にリモートワークが進み、人と話をしたり部門間で協調したり、もしくは社内の壁を壊して社外の人たちと何かを進めるにあたっても、その面倒くささが顕著になりました。
こうした状況でアライアンス事業を打ち立てたのは、覚悟が必要だったかと思います。アライアンス事業を始めて、そのような難しさを感じましたか。
気を遣うことはありますが、難しさは特に感じていません。相手の魅力を発信・発見し、組み合わせるだけだと思います。まず相手の魅力はどこにあるのか、相手が何したら喜ぶのか、というところだけ押さえておけば、アライアンスによってどういうシナジーで、どんな価値が見いだせそうかは話しながら考えていけます。
そうした考え方ができるのは、メディア事業をやっていたからでしょうか。それとも「問題発見から問題解決まで」の経営理念からでしょうか。
パッケージ事業でいろいろな方とお会いしてお話ししますが、商品が出てくるのはあくまでも最後の最後です。お客さまの今置かれている状況や環境の変化、会社の魅力や、これからどのようにしていきたいか、というヒアリングを常に行い、その中でお役に立ちそうであれば商品を提供しています。この考え方は共通していると思います。
2. 大きな潜在力をもつ日本酒産業との共創
このアライアンス事業において、酒輪(シュリン)が立ち上がったきっかけを教えてください。
日本酒はその名のとおり日本のお酒ですが、日本ではワインなど海外由来のお酒の方が人気といった不思議な感じもあります。日本酒はもっとポテンシャルがあると思っているのですが、いったい何が起因しているのか。これについてある酒蔵さんいわく、「うちの業界にはね、ガラスの天井があるのだよ」と。
つまり見えない縛りや、「あまり目立ってはいけない」という雰囲気があるのだろうと思います。というのも、日本酒産業は昔から続く業界です。今は経営者層も変わっていって異なる流れも出てきたかとは思いますが、それでもさまざまな足かせがあることは推測されます。しかし、それを逆に外から見ると、もっと伸ばせるところがあるということ。今、その可能性を探しているところです。
かつて酒税は日清・日露戦争の軍事費として使われるなど国にとって大きな財源となっていたために、日本酒業界は既得権益が強くなってしまったこともあるかと思います。こうした雰囲気を変えていく動きがあるのでしょうか。
そうですね。今は経営者も変わりずいぶんいろいろな方々が出ているものの、約1500もの酒蔵があると言われる中で皆さんがご存じの銘柄は非常に少ないと思います。ですから、一部の酒蔵だけが目立って終わるのではなくて、もっと業界全体で何かできないかと思い、「酒輪」を始めました。
「酒の輪と書いてシュリンと読みます。基幹事業のシュリンクとかけまして……(笑)このネーミングは私だけでなく社内で考えました。」
この事業でデジタルラベル、NFT(Non Fungible Token;非代替性トークン)を活用したというのは結構ユニークだと思いますが、なぜこれをやろうとしたのですか。
長年、既存の流通に閉じて商売をされている業界ですから、新しい流通を持ち出すことで、これまでの流通を乱すことは避けたいと思っていたからです。
ただこのNFTの活用は時期尚早と言いますか、いつでもできるように準備はしているものの、世の中へ打って出るにはまだ早いと感じています。この空中戦はもう少し置いておくことにし、地上戦に切り替えたところです。
この空中戦の実現は、既存の商流、商習慣などが壁になるのでしょうか。
そうですね。逆に近年は通信販売での流通も一般的となっていますので、買い方さえ分かれば可能性はあると思い、今は商品開発に取り組んでいます。
(※編集部注:2023年取材当時。当該商品は2024年7月より「地球の歩き方オリジナル日本酒」として販売開始。株式会社地球の歩き方が出版する「地球の歩き方」国内版シリーズと連動し、その地域の酒蔵の日本酒を販売するコラボプロジェクトで、コラボ日本酒ラベルの正面デザインは地球の歩き方ガイドブックの表紙デザインがそのまま表現され、裏面では都道府県情報・観光地スポットが紹介されている。)
これより先は会員限定コンテンツです。
関連記事
【特別対談】EU ドイツのIndustry4 0の現在地と日本製造業が取り組むべきDXのNEXT ACTION
- 動画 2025年3月19日
- Collaborative DX 編集部





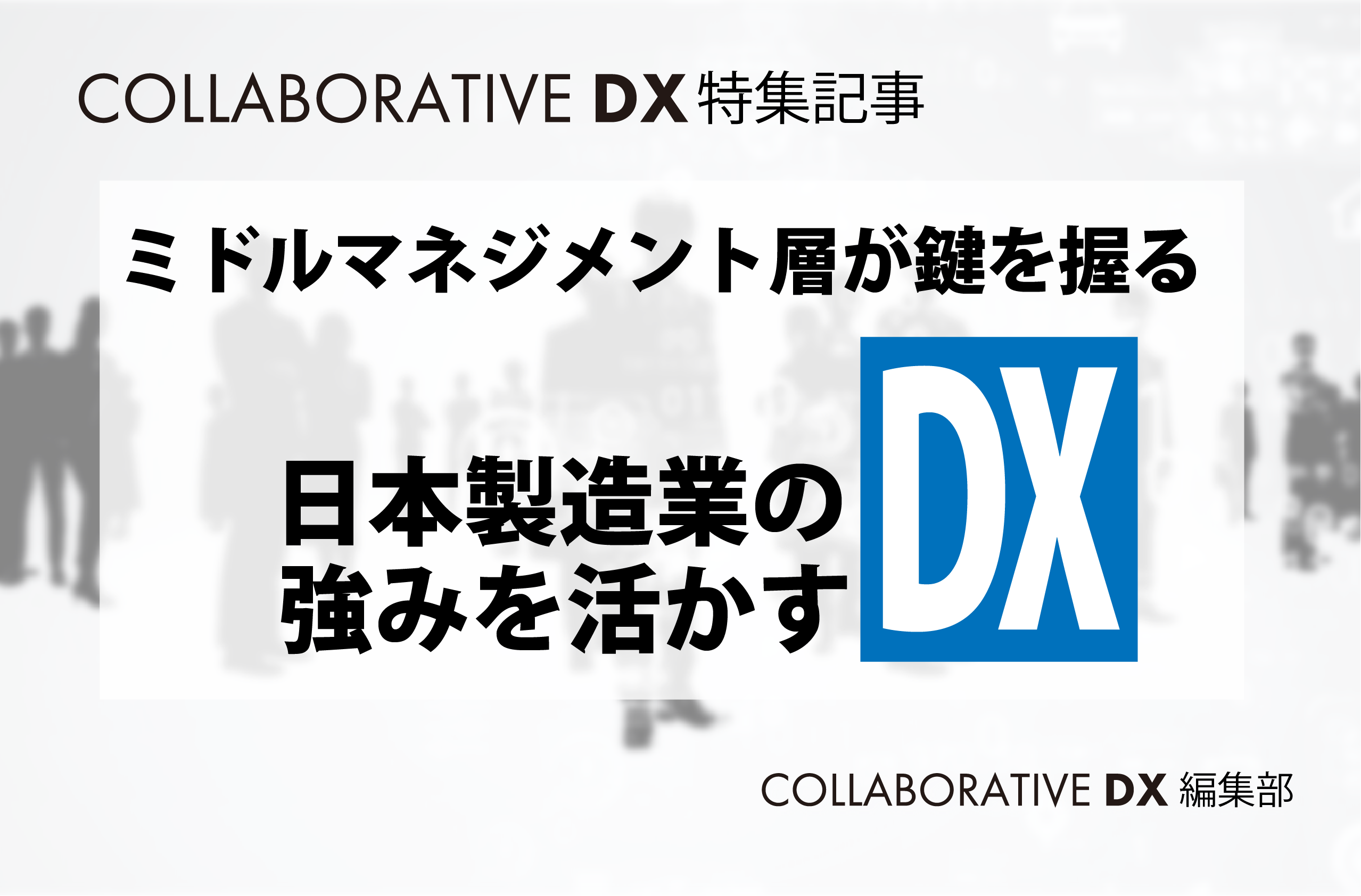

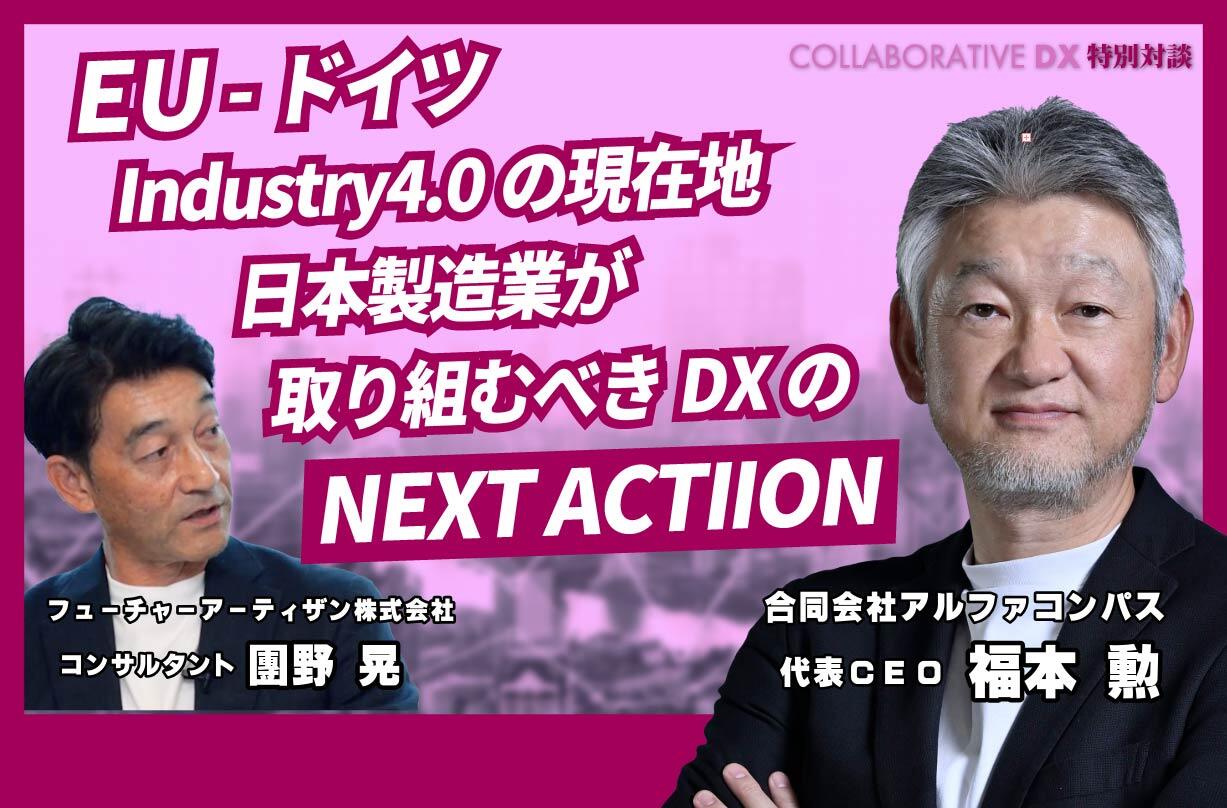

この記事について
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ