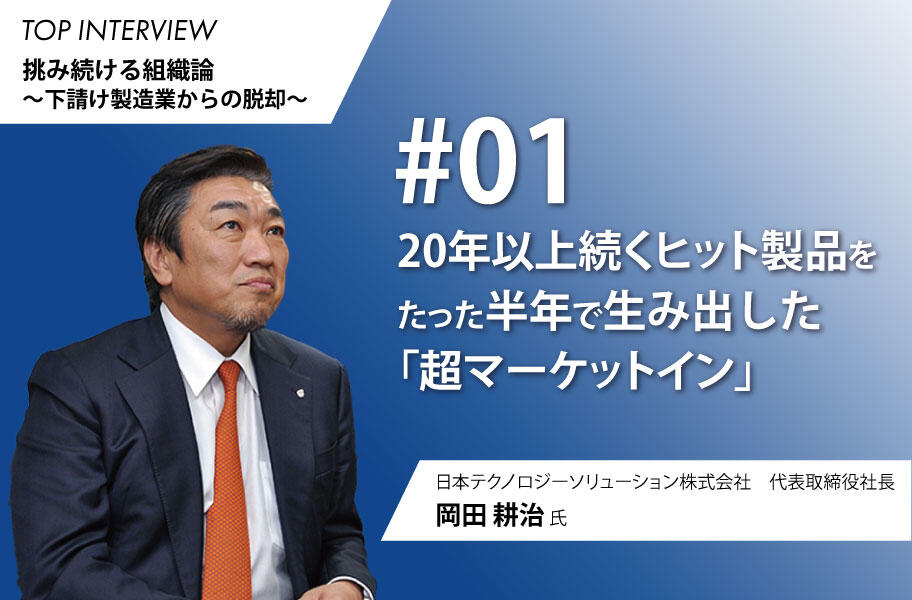
革新的な技術や製品を作り、世に送り出すだけでなく、他の企業と事業を共創し、メディアとして情報発信もする。製造業という枠にとどまらない多様な事業を生み出し新しい時代を創る、それが日本テクノロジーソリューション株式会社である。まるでベンチャー企業のように挑戦的な事業内容だが、その挑戦への始まりは50年ほど前にさかのぼる。
アジア諸国が台頭し始める中での事業転換、そして拡大を推進した「超マーケットイン」とは何か、代表取締役社長の岡田耕治氏のお話を伺っていく。
就任当時からの変わらない想い
まずは簡単に自己紹介や、貴社の経営理念をお伺いできますか。
日本テクノロジーソリューション株式会社の代表取締役社長の岡田です。1999年に社長に就任し、丸25年になります。
就任当時から、今までの製造業の物差しを変えたい、もっと言うと、中小企業の物差しを変えたいと思いやってきました。特に就任当時は業種業界ごとにある既存の枠組みが強かったのですが、そもそも、業種業界という言葉はナンセンスだと思っていました。なぜなら、自分たちの事業の定義づけをするのではなく、顧客にとっての価値を明確にするべきだと思うからです。
また、どうしても中小企業には「つらくて厳しくて、やはり大企業には勝てなくて…」という、そんな世界観があると思います。このように感じているほとんどの中小企業は、親会社みたいに顧客を見ている。つまり「顧客に指示されたことしか考えなくなっている」ことが良くないところだと思います。
一方で、私たちは物を作って売っている会社でもありますが、それだけでなく「ソリューションを売る」ということを、設立当初から考えていました。それは何か1社で問題解決する、ということではありません。会社のロゴマークの下に「ソリューションコーディネーター」という文言をつけていますが、これは「問題発見から問題解決までをコーディネートできる存在になりたい」という思いからです。
今は「とんがった」会社が勝てる時代だと思いますので、そうした会社の集合体になっていきたい、そしてその一部になっていきたいと思っています。
日本テクノロジーソリューション株式会社のドメイン「solution.co.jp」は1999年に取得。
「自分でもよく取れたなと思います(笑)」
ブラウン管から液晶・プラズマへ……早くもアジア諸国が台頭
物を作って売るだけではなく「ソリューションを売る」、というのは非常に興味深いですね。貴社の歴史について、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
1999年に社長を引き継いだ当初は、ほぼ、民生用(家庭用)テレビのブラウン管の検査装置を作っていた企業でした。ただし、対象はある日本企業のブラウン管の検査装置に限定されていました。その企業が悪いわけではありませんが、ブラウン管を作っている電機メーカーは日本にたくさんあっても他社に展開できず、価格の決定権もなく……もう、手足を縛られている感覚でした。こちらから価格を提案しても、結果何十%の値引きを依頼され、断ることはできない業界だったのです。
したがって、「こうした下請け構造そのものから脱却しないといけない」という思いがありました。しかし既存事業の割合がほぼ100%でしたから、そこから一気にシフトするのは難しいところがありました。
そこでまずは新規事業を創り、少しずつ広げていこうということで、事業を引き継いだ翌年の2000年になったときに、ブラウン管ではない液晶・プラズマの分野の検査装置を考えました。
当時、それまでとは全然違うルートでベンチャー企業がプラズマテレビの検査装置を作っていて、その電装部分を受注できました。電装部分だけでも2000万円と、それなりの金額感があったので、もうそこで食いつないでいけるかもしれないと思っていました。ブラウン管はなくなる可能性が高いけれども、液晶・プラズマ含めたディスプレイで見れば、まだ残れると思いました。
しかし、その3カ月後にプラズマ検査装置の2号機を作るという話が出たときに状況が大きく変わりました。
当時「グローバル調達」という言葉が出た頃で、私たちの作っていた電装設備も、「韓国や台湾、中国の企業だと3分の1の700万円で作れる」といった話を聴き、「それだったらもう無理だな」と思いました。
車と同じように日本を代表する製造業だった家電、その中でも家電の王様と言われたテレビに携わった身で言うと、もうブラウン管だけではなく、液晶もプラズマも日本では作れない。「この業界は終わるな」というのを、2000年の時点で気付けたというのは非常に大きかったと思います。
2000年当時は液晶・プラズマへの設備投資を始めて戦いの激化が始まる入口に至ったところでした。それまでのブラウン管は、まさにすり合わせ技術と言われるようなアナログ要素も非常に強かった一方で、液晶やプラズマというのは、どちらかというとデジタル的に設備を置いて量産を図る、といったイメージで捉えていました。
そうした産業の違いもあり、設備投資がグローバル調達で3分の1になると言われると、日本で作る意味はないのではないかと思いました。そして、「機能的価値だけでの勝負には限界があり、このままアジアが台頭するなら勝ち筋は見いだせない、であれば、この競争から逃げなくてはいけない」と思ったのです。
当時、日本企業が大きく設備投資したニュースを懐疑的に見ていましたが、結果としてやはり当時出てきたアジアのメーカーが台頭しています。
「何か」「新しいこと」で考える、超マーケットイン
家電産業の変化を予見されたこともすごいと思いましたが、そこからのシフトされたことが素晴らしいと感じました。勝ち筋が自分の中で腑に落ちてなくても同じ事業にずっとしがみ付く、というケースがよくある中で、そこからシフトすることは決して簡単ではなかったと思います。既存事業が一定の売上で継続する中で、事業転換しようと思われたのは、何かきっかけがあったのでしょうか。
実は事業を引き継いで数か月した頃、1999年の11月26日……と日付まで覚えているのですが、株式会社エイチ・アイ・エスの澤田秀雄さん(現取締役会長)と初めてお会いしました。そのときにアドバイスを頂こうと思ったんです。今思うと言い訳がましいのですが、「弊社はブラウン管をやっていまして、これからどういうふうにしたらいいですかね」と聞いたのだと思います。そのときに澤田さんは一言、「何か新しいことをやってください」とおっしゃった。
「何か」「新しいこと」って、二つの条件しかないですよね。そして「何か」というのは何でもいいし、その上で「新しいこと」という、この2軸で考えた場合に物事をすごくシンプルに捉えることができました。
将来性のない事業を親から引き継いだとか、悲劇のヒロイン的に言うことって可能じゃないですか。でも「こうして言い訳しているのは私自身であって他の誰でもない」そう思ったら悔しくて。「それまでのつながりのようなものを一切断って、ちょっと違うこと・違う路線をやっていかなければならない」と覚悟を決め、先ほどの「何か」「新しいこと」の二つを条件に考え始めました。
そしてまずは業界を変えようと思い、私たちの期初となる2000年10月に、「電機業界しか今まで知らないけども、食品や医薬品化粧品の分野に行きます」「そこで使ってもらえるような装置を開発します」と宣言しました。本当に何もないところからのスタートでしたが、実際に2001年の4月から今後の将来や新規事業を考えるための経営改造会議を、私と技術者2人の3人で始めました。会議の中で、まずは自社が現状どういう会社かを明らかにした上で、将来どうなりたいかを決め、そこに至るまでのプロセスを作っていきました。そして、そのときに決めた事業が、今の主力事業であるパッケージ事業です。
なぜそこでパッケージ事業を選んだのでしょうか。
熱と制御といった要素技術を持っていた、という技術面もありますが、大きくは市場から入った、という点ですごく変わった開発だったと思います。
液晶・プラズマの苦い記憶から、アジアと戦わないことを決めましたが、これは良い決断だったと今でも思います。戦略とは戦いを省略すること、と言われることもありますが、本当にそうだと思います。あのときにアジアの企業と同じ事業で正面から勝負したら大変なことになっていたと思います。
例えば台湾の企業などの作る安い設備に対して、当時の日本ではあまり評価されていませんでしたが、率直にすごいなと思っていました。だから台湾と戦うことはやめて、今では台湾企業とも仲良くお付き合いさせてもらったり、設備を購入させてもらったりしています。
当時、アジアの空港にある看板は、日本の電機業界の会社ばかりでした。ジャパンアズナンバーワンの臭いが残っている感じで、どの空港に行っても日本の電機メーカー、時々トヨタ、といったところでした。
そうした状況においては、他のアジアの国々の人からは、日本の電機業界がすごく夢の世界のように見えるだろうし、そんな日本で使ってもらえるようなものを開発しよう、いつか日本を絶対抜かしてやろう、という機運というのは当然高まると思っていました。
だから、国際的に目立ってない業界ってどこかなと思ったときに、当時の日本の食品メーカーは日本内需を狙っていてあまり海外で目立ってないですし、化粧品メーカーも当時は国内を見ていました。このような国内市場を主要なターゲットにしている業界を狙っていこうと考えました。
結果として、ターゲット市場は食品、医薬品、化粧品の3品業界としました。要はアジア諸国が入ってこない市場を見たときに、ここだったら可能性があると思ったのです。
マーケットインを掲げながらも自社技術をどう売るかという商品開発を進めてしまう、ということは製造業だとよく起こりますが、貴社の場合は完全にマーケットから入ったのですね。
そうですね。このように完全に市場から入ることを我々は「超マーケットイン」と呼んでいます。プロダクトアウトは自己満足と考えていて、たしかに良くないと思います。ではマーケットインがいいのかというと、それも顧客迎合だと考えており、これも良くないと思っています。お客さんの言いなりになっているのがマーケットインだと思われている節がある。
では「超マーケットイン」は何かというと、「先読み解決」だと考えています。市場が気付いてないところで問題の解決を提案できれば、何か価値を提供できると思っています。まさにそれを具現化したのが、パッケージ事業の主力である熱旋風式シュリンク装置TORNADO®(トルネード)なのです。
結果として、2001年の4月の経営改造会議から、3か月で技術的な要素に落とし込み、その後10月には販売開始しました。かなり短期間での開発ができたと思います。
非常に短期間での開発ですが、今も貴社の主力製品ですよね。マーケットにとっても革新的な、「何か」「新しいこと」だったのでしょうか。
実際、シュリンク包装という技術は何十年も前からありましたし、特に我々が新しいことをやったわけではありません。ただ、それまでの装置では、パッケージの仕上がりが悪いのは当たり前で、品質を満たさないものが多く廃棄されている状況が普通でした。
一方、電機業界で育ってきた僕らとしては、それが普通だというその現場を見たときに「勝てる」と思ったのです。歩留まりが悪くなるというのは致命的な製造ラインの欠陥があるということですからね。こうした視点や、僕らの技術力・完遂力というのは、業界にとっては革新的だったと思います。
だから日常に慣れて当たり前になっている状況の人たちに対して、「こうしたらこういう結果を生み出せますよ」というのはまさに問題発見からの問題解決でした。
機械の正露丸を目指して
当時「何か」「新しいこと」であったパッケージ事業に参入されてから20年以上経ちますが、参入して良かったことはありますか。
やはり事業の安定性があります。ネガティブに聞こえるかもしれませんが、事業に安定性があるということはすごくいいことだと思います。
例えばコロナ禍では、化粧品の売上は下がった一方で、逆にウイルス除去系の商品や、巣ごもり需要で高級志向のドレッシングなどはずいぶん上がりました。このように、さまざまな産業市場で使われることで、需要の上がり下がりに対応できるためすごく良いなと思っています。
これは、かつて一企業のブラウン管検査装置の一本やりで依存していた反省から、販路ができるだけ広いところを探した結果です。
また、最近の環境問題にも寄与できると考えています。
最近もあるアメリカのフィルム素材メーカーと、世界の潮流についてお話しする機会がありました。商品を見せるためには、パッケージの機能は不可欠です。そして、それを持続可能な状況にする一つの方法として、環境に良いフィルムを使うことが挙げられます。ところが、こうした新しい素材が出てきても、実際に見栄えのいい包装にするためには、いい装置が必要となるわけです。私たちはそんな装置に位置づけるような商品開発をしているつもりですし、こうした側面で環境寄与をしていると思います。
 他にも、今、ビン不足の問題にも対応しています。例えば日本酒の場合、遮光性の観点から緑や茶色のビンを使っていますが、こうしたビンは不足しています。それに対して、シュリンク技術で遮光性フィルムをビンに密着させたパッケージとすることで、機能性も担保できますし、ビン不足にも寄与できます。
他にも、今、ビン不足の問題にも対応しています。例えば日本酒の場合、遮光性の観点から緑や茶色のビンを使っていますが、こうしたビンは不足しています。それに対して、シュリンク技術で遮光性フィルムをビンに密着させたパッケージとすることで、機能性も担保できますし、ビン不足にも寄与できます。
昔はシンプルな形状のビンや缶が多かったですが、今はペットボトル、それも密閉ボトルや特殊な形状の容器が増えたように思いますが、それぞれのパッケージは容器にぴったりフィットさせた上で文字やデザインを表現することが求められていますね。また先ほどの環境への対応や遮光性、物によっては耐薬品などさまざまな要求がありそうです。
実はこのトルネードの開発当初、機械の正露丸を目指そうと思いました。どういうことかというと、正露丸がなぜ腹痛に効くのか、つい最近までわかっていなかったそうです。でも、とりあえずお腹が痛ければ正露丸でも飲んでおけ、と言われて僕らは育ちましたよね。何か困ったときには○○……そんな位置づけになる製品を目指してトルネードを開発しました。トルネードで既存のやり方ではない道筋はつけたと思いますし、さまざまな問題に対応できているのではないかな、と思っています。
公開済
プロフィール
岡田 耕治(おかだ こうじ)
日本テクノロジーソリューション株式会社
代表取締役社長
 以前はコンサルタント会社で『組織変革』をテーマに、企画立案を企業に対して行う。1999年に2代目で現在の会社を引き継ぎ、自社ブランド製品開発・販売、業態転換を果たす。現在は自身の実践的経験を踏まえ、各企業で新規事業開発プロジェクトを推進している。
以前はコンサルタント会社で『組織変革』をテーマに、企画立案を企業に対して行う。1999年に2代目で現在の会社を引き継ぎ、自社ブランド製品開発・販売、業態転換を果たす。現在は自身の実践的経験を踏まえ、各企業で新規事業開発プロジェクトを推進している。
岡田 耕治氏 Facebookアカウント
PURPOSE COMPANIES
関連記事
【特別対談】EU ドイツのIndustry4 0の現在地と日本製造業が取り組むべきDXのNEXT ACTION
- 動画 2025年3月19日
- Collaborative DX 編集部




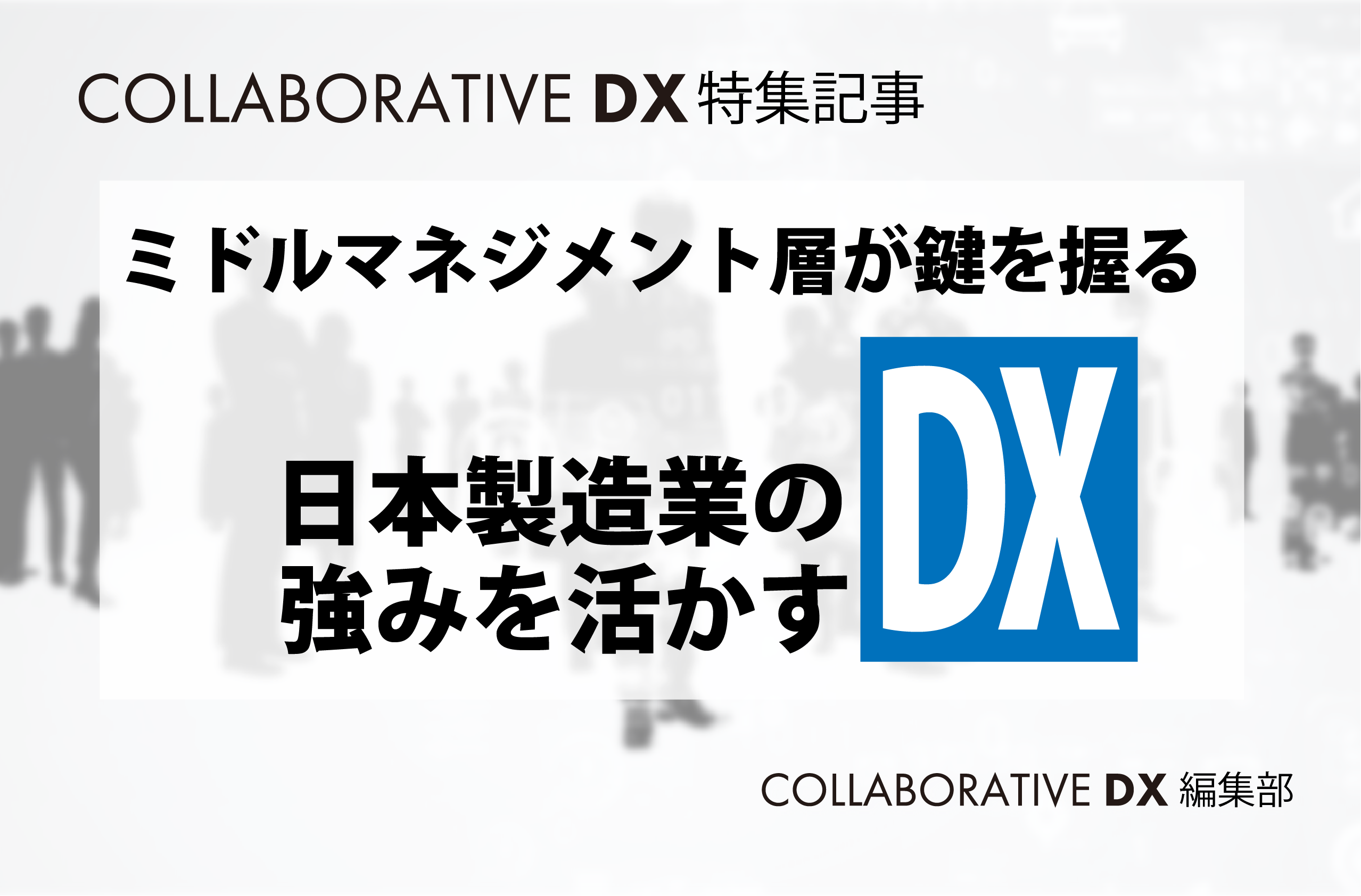

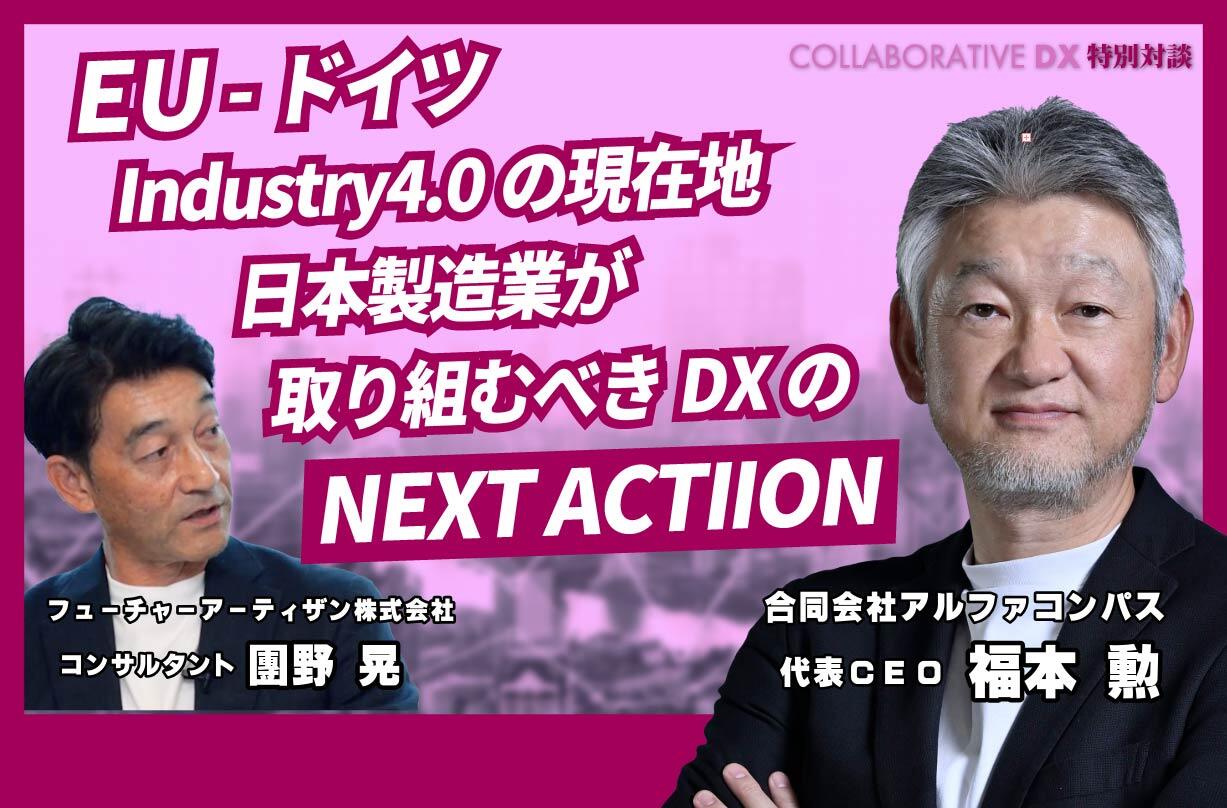

この記事について
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ