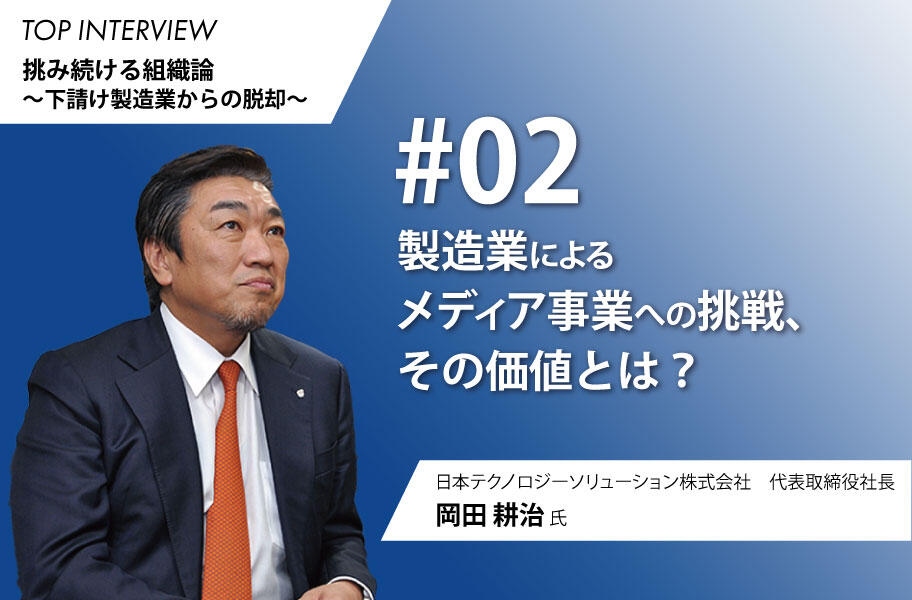
革新的な技術や製品を作り、世に送り出すだけでなく、他の企業と事業を共創し、メディアとして情報発信もする。製造業という枠にとどまらない多様な事業を生み出し新しい時代を創る、それが日本テクノロジーソリューション株式会社である。まるでベンチャー企業のように挑戦的な事業内容だが、その挑戦への始まりは50年ほど前にさかのぼる。
見事な事業転換で立ち上げ、成長中のパッケージ事業を持つ同社が何故メディア事業を始めたのか、代表取締役社長の岡田耕治氏のお話を伺っていく。
もう一つのホウソウ事業
岡田様はパッケージ……つまり包装(ホウソウ)事業のほかに、放送(ホウソウ)事業ともいえるメディア事業も立ち上げられたのですよね。こちらの理由もお聞かせいただけますか。
そうですね、メディア事業を2008年に立ち上げましたが、ここには二つの理由があります。
まず、パッケージは、パッケージメディアという形でメディアにつながる媒体だと思っていた、というのが一つ目の理由です。
元より、パッケージが持つメディア的な役割はあると思っていました。フィルムのデザインが違えば製品の売上は変わります。中身が一切変わっていなくても、そのパッケージのデザインが変わるだけで売上や利益が変わる、というのは非常に面白いところでもあります。
また、パッケージ表示の面積が20年前と比べると増えています。メーカーさんとしては商品をもっと良く見せたいという思いから、表示面積は増える方向に行くだろうと当時から想定していました。
その中で、例えばパッケージに記載されたQRコードなどを通じて、パッケージからさらに外のメディアに飛ばすような話は絶対出てくるだろうと思っていました。
二つ目の理由としては、パッケージ事業での成功経験もあります。パッケージ事業を、あらかた何もないところから生み出したことにより「少人数でもしっかりマーケットニーズをつかめれば、自社ブランドを持てるし、新しい提案ができる」ということを実感しました。
日本には無数の技術力がある一方で、それがマーケットニーズになかなか結びついていないと感じています。ですから、それを分かりやすくご紹介できるようなメディアがあれば、非常に役に立つのではないかと思った次第です。
こうした思いで運営していますので、私たちのメディアの取材対象は製造業に絞っています。
最近は、かっこいいオウンドメディアを作ってメーカーから自社発信していく、というケースもありますが、当時そういったことは全然ありませんでした。ただそれでも、メーカーさんはもっと魅力を発信した方がいい、そして、どのメーカーも実はすごいことをやっているということを、外からも中からも気付いた方がいいと思っていました。
技術者がCADで図面を描いたり、ソフトウェアをプログラミングしたりと、現場で目の当たりにします。技術者にとっては当たり前だから、普通にやっていますが、技術畑にいなかった私としては、本気で感心します。こうした彼ら技術者のすごさを、もっとアピールした方が分かりやすいと思っています。
メーカーの方は皆さん本当に素晴らしいことをやっているのに、会社の中の限られた方としか会っていない上に、自分の仕事を発信する機会もなかなかありません。特にB2Bでは、自分たちの素晴らしさを実感できている人は少ないと思います。
いろいろなメーカーさんにお邪魔する中で、私たちの経験した下請け分業構造だけでなく、社内分業にもなっていることに気付きました。次の工程はお客さま、ということはメーカーさんがよくおっしゃるのですが、最終形がどうなっているか、現場の技術者は想像がついていません。
自分がやっている目の前の作業しか見えなくて、プライドも自信も何もない。ただ言われたことをしっかり納期どおりにこなさないといけないというプレッシャーで、なんだか顔色が悪い……。
これは非常にもったいないと思いました。可能な限りその製品の最終形を見せて、どんな製品ができるのかが分かれば絶対に面白く感じてもらえると思います。技術者が、自分はここの部分に関わったのだと自慢もできる。そういう状況を作りたいなと思いました。
このように自身がかかわったものが世に広く知れわたるということが、私たちがパッケージ業界に入った理由の一つでもあります。私たちがかつて作っていたブラウン管の検査装置は、生産ラインにすら乗っていない、抜き打ちで使う検査装置でした。品質管理・品質保証の分野の方以外は誰の目にも触れない黒子のような製品です。しかし、パッケージなら多くの人が見ますので、自慢できますよね。これは大変重要だと思っていました。
 「社長の趣味か!」とよく言われましたが、結構真面目に考えてやっています。以前から、パッケージが果たすメディアとしての役割は大きく、親和性は高いと思っています。
「社長の趣味か!」とよく言われましたが、結構真面目に考えてやっています。以前から、パッケージが果たすメディアとしての役割は大きく、親和性は高いと思っています。
社長自ら、新卒OJTと新規事業立ち上げを並行
実は、メディア事業を始めた時期は、新卒採用を始めようと思った時期と合致しています。2004年に「優れた技術を優れたビジネスにする」というコンセプトを打ち出して、コンサルティングのようなことを私自身も幅を広げるためにやっていこうと思い、社名変更から始めた頃でした。
こうした取り組みの中で、「製造業という枠組みに捕らわれたら良くない」「会社の文化を変えよう」と思い、人を、新しい風を入れるため、新卒採用を意識しました。実際には2006年から新卒の募集を始め、2008年の4月に入社という形になるのですが、その間に先ほどの理由でメディア事業を始め、さらにこれを新卒採用の社員に任せようと思いました。
そして、新卒採用した5名全員をメディア事業に配属し、スタートしました。
新入社員が5名ですか。どういったところから始められたのですか。
100社無料取材です。これは経営者として、怖さを感じながらやりました。無料だからこそ研修期間と思って、社会に育てていただこうと思いました。
弊社は少ない人数でやっていますので、大きな企業のようにOJTリーダーなど設けられません。直接私が5人の面倒を見ました。社長自らがOJTをしながら、会社で事業を立ち上げる、というのはなかなかないと思います。3か月で100社やり切って、7月からは社員に驚かれながらも有料に切り替えました。
最初はWeb記事として写真とテキストを中心に取材をしていましたが、動画は絶対に流行るだろうと思い、サイト内に組み込むような小さい画面でのコンテンツを用意していました。
そして、テレビのCM枠を買って映像を流し始めた2010年頃から本格的に映像制作の方にシフトし、大きな効果を感じたところです。
当時、製造業に特化したテレビ番組は既にあり、2001年に私たちの技術者がその番組に出たいと言っていたのが印象に残っています。ただ、動画配信はおろかSNSも流行っていない頃ですから、既存のメディアによる番組はあっても、自身でこうした発信をしているメーカーはほとんどなかったと思います。
新入社員と社長以外の社員の方は、どういう思いで見ていたのでしょうか。
元々いる社員は従来どおり真面目にものづくりを続けていましたので、もしかしたら、彼らが稼いだものが新規事業に持っていかれることへの抵抗感はあったかもしれません。ですから彼らには、「3年間、新入社員には絶対に文句や陰口を言わないように」と伝えた上で働く場所も分けました。
価値は無限 ~メディア事業から得られた無形の価値~
私たちのメディアで開催している経営サロンにご登壇いただいた慶応義塾大学の岩尾俊兵先生が、「価値が有限だという認識があるから対立が起きる」と仰っていました。[*第7回経営サロン]
例えば会社のトップラインが、従業員の働いた時間により決まる有限なものだと思うと、既存事業を支える社員はこうした新規事業に対して「自分が稼いだ売上を奪っている」といった批判的な視点で捉えてしまう。しかし、メディア事業のように無形資産が産み出す価値は、未来にそのトップラインの壁を壊してくれる可能性があり、どんどん膨れ上がる無限の領域に踏み込むと考えると、本来みんなが応援しないといけないですよね。
まさにその通りだと思います。やはり新しい価値を作っていきたい。そして有限ではない無形の価値を生み出すことが重要。それは、メディア事業に限ったことではなく、パッケージ事業(包装機械分野)のように有形なモノを売るビジネスでも同じです。問題を発見し、解決策を装置にハード・ソフト含め具現化できる。そのノウハウという無形のものこそ価値があります。
以前、パッケージ事業で、新商品の熱旋風式シュリンク装置TORNADO®(トルネード)を公開した際に、何社か中国から来られた方がいらっしゃいました。実際に製品を見ていただくまでは、皆さんすごくポジティブな反応をされますが、最初に見積を出した時点で、価格を見て諦めてしまう方がほとんどでした。
こうしたことが何度かあった中でお迎えした方で、実際にやり取りをして製品を見ていただき、良い反応も頂きました。しかし価格を聞いてその方も同じように高いと思われてしまうだろうと思っていました。
私たちは何十年もこの業界でやっていることもあり、アジアでは「包装業界のルイ・ヴィトン」などと言われています。その方にも「高いですよ」と最初にお伝えした上で見積を出したのですが、その方は顔色一つ変えずに「いや、価格より価値ですから」とおっしゃったのです。
「最初から価格の高さは分かっている。それよりも、日本という難しいマーケットにおいて、この包装業界で生き残っているという、あなた方が経験したそのノウハウという価値を買うのです」と。
このとき率直に、「日本はいよいよ危ない」と感じました。
当時の日本でも「価値が重要」といいつつ、原価管理のような値付けや買い方ばかりでしたね。価値ではなくコストだけを見ているような人も多かった。それがイノベーションを阻害した側面もあったのではと思います。
そうですね。仮に日本製の方が機能は高く、ランニングコストは下がるとしても、「初期導入コストが高いと導入できない」といった感覚の企業が多かったかもしれません。「日本製は価格が高くても長く使える。ただ、中国製の方が3倍壊れやすいとしても、価格が三分の一以下だったら中国製を何回も買う方がいい」といった話も実際にありました。不良品や故障の対応でのロスなどは考えられないのでしょうか。そのような中、中国から来られた方の中から「価格より価値」という価値観でビジネスをされている方が、ついに私たちの前にも現れだしたというのは衝撃的でした。
このとき、従来どおりパッケージ事業の一本やりだと怖さを感じたと思いますが、メディア事業のような新しい事業を立ち上げていたのは安心感にもなりました。特にメディア事業は設備投資が必要な事業ではないので、やめない限りは続けていけると思っています。何より新しいサービス価値を作るのは怖さより面白さの方が大きかったです。
メディア事業をやっていて一番良かったことは何でしょうか。
もう間違いなく、大企業の経営トップにお会いできることです。発信や取材を通じて、普段会えない方たちとの関係構築ができます。極端に言うと、利益を求めず原価でいいと当初は思っていました。これは新卒入社の社員とやった発想の根底でもあります。
メディア、特にテレビ番組は取材先のトップが出てきます。大企業のトップのような普段はお会いできない方に会えるというのは、大きな価値だと思っています。広告や展示会などのセールス的なマーケティングでは、お金をかけてもトップの方に売り出すなんて無理ですから。
私たちはメディア事業を通じて、日産自動車の元COOの志賀俊之さんやカルビーの元CEOの松本晃さん、積水ハウス元会長の和田勇さんにもお会いしました。
こうした方々に直接インタビューさせていただけるのは、ありがたい限りです。直接お会いすることで、その方の持つ空気感、すごみや目の奥の光を感じられます。
以前、先述の志賀さんへのインタビューで「なぜダイバーシティを進めているのか」を質問した際、「(業績が低迷し、外資系企業の傘下となってしまった)かつての日産には戻りたくない。今、ダイバーシティへの取り組みを進めないと、当時に戻る可能性がある」と答えていただきました。こうした言葉を、何も介さず直接受け取ることで伝わってくる本気度、温度感はありますよね。インタビューをする会議室でじかに目の当たりにするインタビュー相手のすごさは、従業員も感じた方がいいと思いました。
こうした方々にお会いしようと思っても、包装機械のトルネードを持っているだけでは、いきなり電話をしてアポイントを取るなんてできません。会社として何か武器を持つために、どうすれば受け入れてもらえるか?これを考えたときに、メディア、そして無料取材を始めたのですが、結果に繋がりました。
このような素晴らしい方々とつながること、その方々の生の声を聴き、空気を感じられることは、メディア事業がもたらしてくれた大きな価値です。
岡田氏にとっても挑戦であったメディア事業では、挑戦する人「挑人(ちょうじん)」を様々な媒体で紹介している。
公開済
第1回「20年以上続くヒット製品をたった半年で生み出した『超マーケットイン』」
プロフィール
岡田 耕治(おかだ こうじ)
日本テクノロジーソリューション株式会社
代表取締役社長
 以前はコンサルタント会社で『組織変革』をテーマに、企画立案を企業に対して行う。1999年に2代目で現在の会社を引き継ぎ、自社ブランド製品開発・販売、業態転換を果たす。現在は自身の実践的経験を踏まえ、各企業で新規事業開発プロジェクトを推進している。
以前はコンサルタント会社で『組織変革』をテーマに、企画立案を企業に対して行う。1999年に2代目で現在の会社を引き継ぎ、自社ブランド製品開発・販売、業態転換を果たす。現在は自身の実践的経験を踏まえ、各企業で新規事業開発プロジェクトを推進している。
岡田 耕治氏 Facebookアカウント
PURPOSE COMPANIES
関連記事
【特別対談】EU ドイツのIndustry4 0の現在地と日本製造業が取り組むべきDXのNEXT ACTION
- 動画 2025年3月19日
- Collaborative DX 編集部




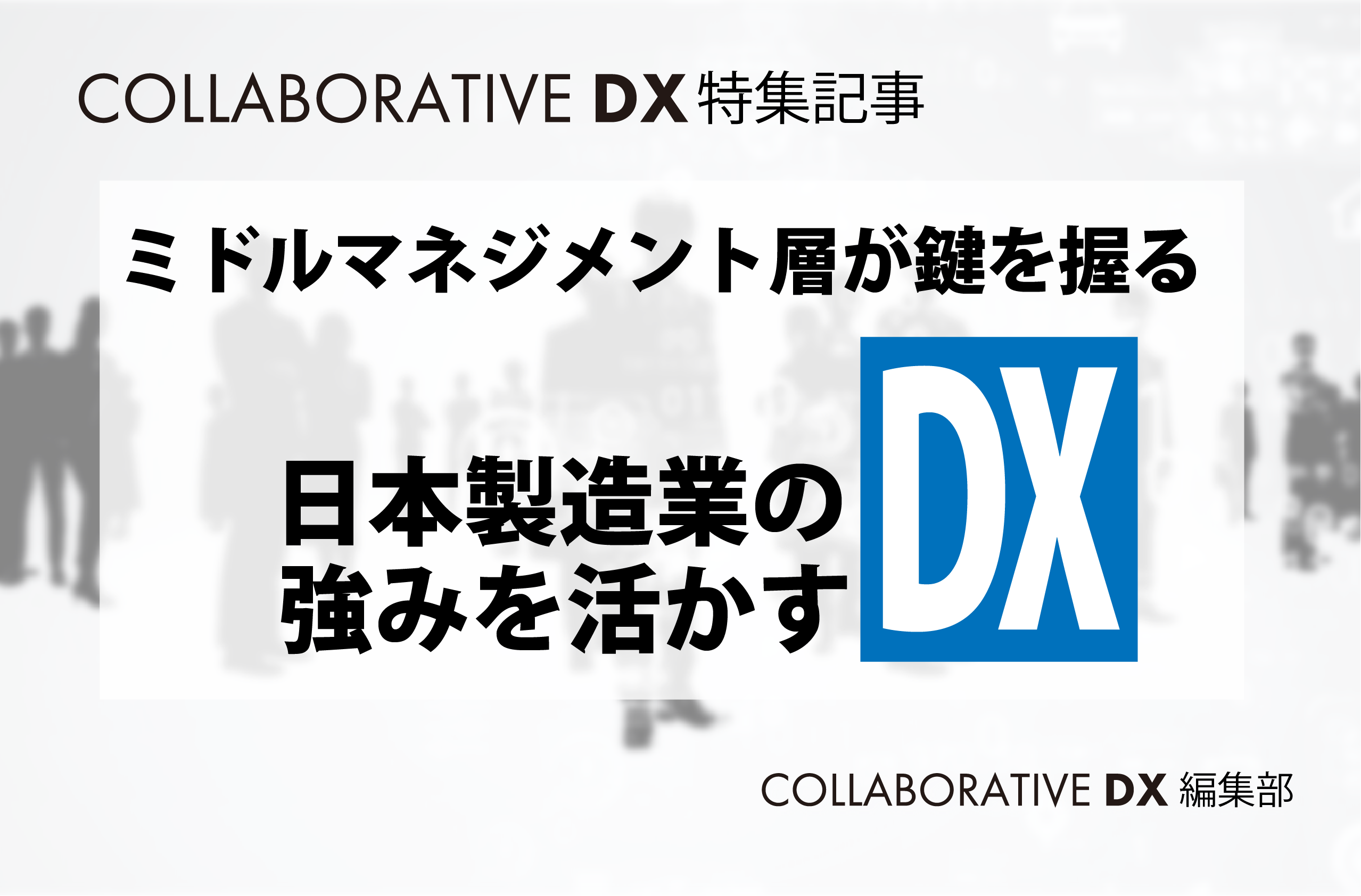

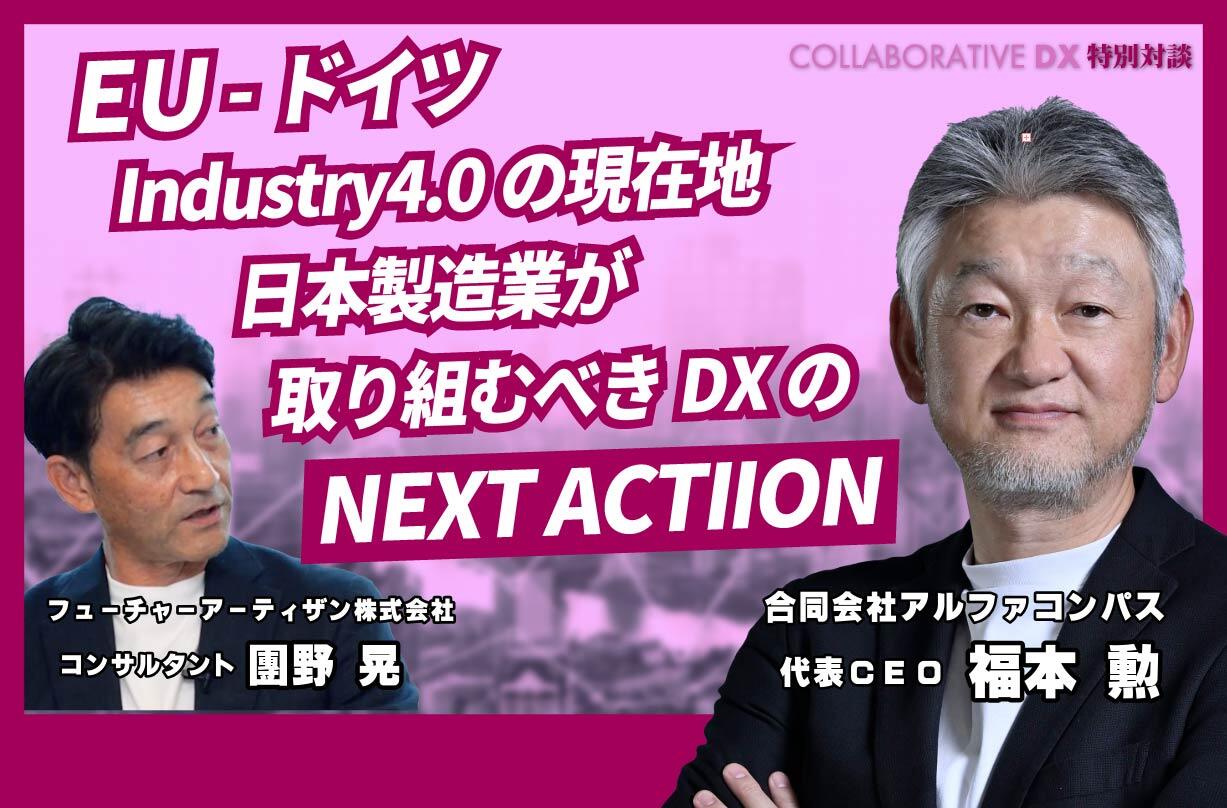

この記事について
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ